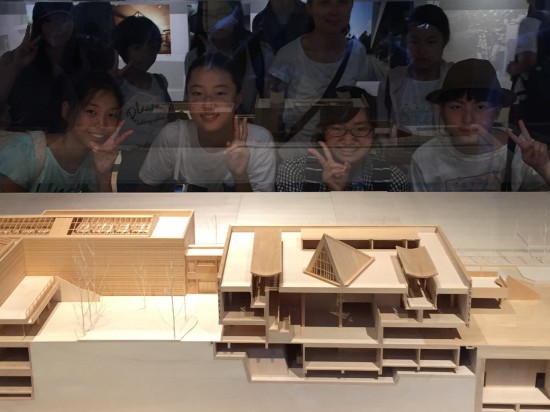[中高生クラス] 2017.06.02
深め、そして伸びやかに
中高生クラス、今年度最初の制作『サザエとサンダル』『パイナップルとミラー』も、折り返しを過ぎました。
持参したサンダルとサザエを工夫して構成し、子供油絵クラスよりひとつステップアップした方法で描き始めた中学生。水曜日のクラスには、初めての油絵に挑戦している生徒もいます。丁寧な観察と豊かな感性で配置、構成を決め、下地作りから着実に絵の具を重ねています。それぞれが持参したサンダルは、どれもその生徒自身の個性を表しているかのようで実に面白く、そこから選ぶ色やタッチも納得してしまうものでした。少しずつ『自分の表現を深める』ことを考えていって欲しいです。
高校生は、初めての囲みモチーフに戸惑いながらも、皆で相談しパイナップルやボウルなどの位置を決めました。モチーフの組み方ひとつで、描くイメージは大きく変わります。最終的に決まったモチーフは、アグレッシブで若さを感じるものとなりました。その周りにぐるりとイーゼルを立て、中学生よりも大きいF10サイズのキャンバスに向かいます。囲みモチーフは観察する空間が広くなり、それに伴い描く方法もより多様となります。それぞれが『この絵で描きたいもの』をしっかりと考え、進めていくことがとても大切です。小さくならずに『伸びやかな表現』を目指していって欲しいです。
ここからいよいよ後半戦。真剣に絵と向き合うと悩みは尽きません。どんどん悩んで納得のいく表現を目指しましょう。