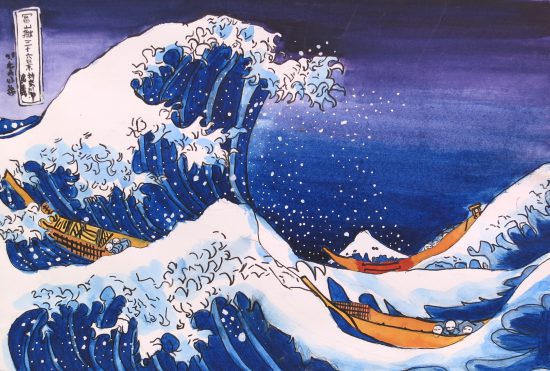[小学生高学年] 2018.08.17
小学生高学年 中高生 鑑賞/夏の美術鑑賞会
夏期休暇の直前である先週の金曜日、高学年・油絵・中高生クラス合同による毎年恒例『夏の美術鑑賞会』を行いました。今年は横浜美術館で開催されている『モネ それからの100年』を鑑賞、OG、保護者の方も含め20名以上の参加となり、当日は台風も心配されましたが、幸いお天気にも恵まれ、夏らしい日差しと共に充実したイベントとなりました。皆様ご参加ありがとうございました。
美術館到着後、学芸員さんによるレクチャーを受け、印象派の代表であるモネの作品と、それらが後世に与えた影響などを解説して頂き、興味がグッと深まったところでいざ鑑賞。大盛況で混雑する中、一枚一枚の作品毎に自分の感想をメモに取る子、友達と意見を交わしながら楽しく進む子、初めて目にする技法、表現に食いつく子など、時間はいくらあっても足りない程。保護者の中にも「しっかり見ます」と音声ガイドを借りて絵画の世界に浸る方も。なんとなく、流しつつの鑑賞を行わないのは、自分の制作に、真剣に取り組んでいる証拠。ここにあるのは全く別の世界のものではなく、繋がっているという感覚、日々の制作の延長線上に、目の前に飾られている作品があるという確信、仲間であるという意識。それらがそれぞれの鑑賞をいかに豊かで実のあるものにしてくれているのでしょうか。きっと、ここでの発見が秋の制作に活かされ、花開いてくれることでしょう。
軽い昼食を頂き美術館を後にし、教室に戻ってきたらお楽しみのかき氷会。クラス、学年を超え、皆ワイワイガリガリかき氷を作っていきました。こんなところでもこだわりを忘れず、それぞれがなんだかやたらと美味しそうなトッピングで仕上げたかき氷で涼を感じる中、普段の制作では見せない、解れた表情で仲を深めていく生徒達。この親睦も、彼らの成長の一助となることは、もう言うまでもありません。クラスが違っても仲間がいる、それはとても心強く、とても嬉しいことです。
夏の開放の中で見つけた『仲間』が、これからのあなた達の制作をきっと力づけてくれることでしょう。
横浜美術館『モネ それからの100年』
https://yokohama.art.museum/