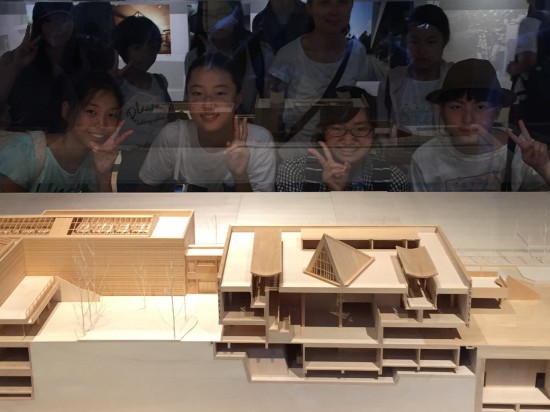[小学生クラス] 2016.09.19
2つの空想画
今月の月・火・水(低中学年)クラスは、「秋の空」からイメージを膨らませて描きます。まずは、秋の空をスケッチしに国際交流センターに行ってきました。からっと晴れた空には、名残惜しそうな夏の雲と、涼しげな秋の雲が混在して雲をスケッチするのに、最高の一日!鱗雲に羊雲。クジラみたいな形もあるよ!あっリンゴ雲! スケッチを終えたら、シャボン玉をしました。 夕焼け雲とともに舞い上がるシャボン玉。子ども達の笑い声も上がって行きます。皆で遊んだ美しい時間が、絵にぐっと力強さを与えると思います。完成をお楽しみに! 月・水の後半(高学年)クラスは、「自分の星」をテーマに、銅版画のエッチングのような線画に挑戦です。地球以外に生命が存在する星があったら、どんな景色が広がっているだろう?今回のルールは、「とにかく線でみっちり描くこと!」のみ。 教科書に落書きするあの感じ。いつもは押さえてしまうあのイメージの広がりをとことん描ききってみよう! 線描の作家に童話画家トーベヤンソン漫画家大友克洋、グラフィックデザイナー永井一正などの本を紹介しました。 「うわー世界観はんぱねえ!」「気持ち悪い〜」という子も。好きも嫌いもいろいろ見てみんなで感想を言い合うのが楽しそう。 アトリエでの空想画は、低学年と高学年では空想の仕方が違うので今回のように内容を変えています。低学年は、現実と空想の境目が薄いので、出来るだけシンプルにどんどん描けるようなテーマを考えています。雲の形を見ただけで、「雲のお城だ!」「おばけだ!」「くじらだ!」と次から次へとイメージが膨らんで行く低学年の子ども達。まさに空想の達人です。 経験と自分の考えを持ち始めた高学年は、現実から空想できる入り口を見つけ自分の空想を広げていきます。リアリティを種に、考えを練り想像を膨らませます。絵を見ると「なるほど〜」と味わい深いストーリーが込められていたりします。よく、高学年の保護者の方からだんだん大胆さが無くなり、 小さく細々してきたけれど、大丈夫かしら?というお話を聞きます。あののびのび描いていたのは、どこへ行っちゃったの?と不安になる気持ち良くわかります。でもそれは 自分に対しても他者に対しても批評する力が育ってきた成長のあかしだと思います。焦らずに一人一人違う成長段階を飛ばすこと無くその時のその子の想像(考え)を見守っていきたいと考えています。