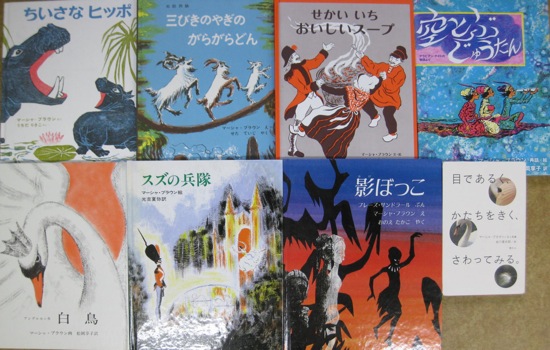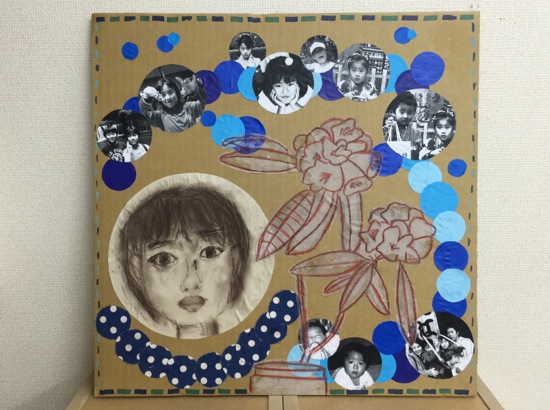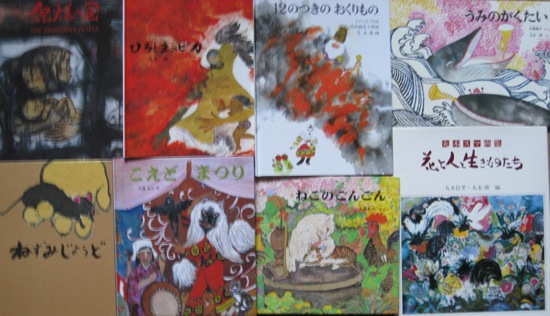[小学生クラス] 2015.09.09
春日/小学生:旅の絵本
小学生クラス(月•水) 2015年9月
◎ 感想/アシスタント:春日千尋
9月の制作は、夏に行ってみたかった場所をゴール
としてその道中を描いた絵本作りをしています。
急に涼しくなって、まだ調子が出ない様子の皆に、
こんな質問から始まりました。
「皆夏休みは楽しかった?どこに行ったのかな?」
皆楽しそうに思い出を話してくれました。
「先生はあまりに日本が暑いから、南極に行って
ペンギンと一緒に遊びたかったです!皆は、自由に
どこにでも行けるならどこへ行きたかった?」
「私はライオンがいるところ!」
「お化けがいるところ!」「宇宙は?」
時間も次元も超えてどんどん想像が膨らみます。
「じゃあそこに行くまでの旅の絵本を作ろう!」
まずは、スケッチブックに、「出発する場所」
「時間」「乗り物」などを考えて「目的地」までの
ストーリーを言葉で書き出しました。
夏の楽しかった思い出も織り交ぜながら自分だけの
旅の物語を作っています。次週から蛇腹の絵本に
色鉛筆で描いていきます。完成が楽しみです!
========================
【子ども美術コース秋の体験日】
☆秋の入会キャンペーン9•10月まで
【体験受講料】 通常1,500円→ 500円
通常レッスンを下記の日程で体験していただけます。
☆見学は随時受け付けております。
◎小学生クラス 前半クラス15:30~17:00
後半クラス17:00~18:30 ※月水のみ
10月5日(月)6日(火)7日(水)
『魚介類』(観察画)
◎幼児クラス 水曜日クラス13:30〜14:30
木・金曜日クラス15:00~16:00
10月 7日(水)8日(木)9日(金)
『かぼちゃとどんぐり』(観察画)
【土曜特別講座 秋のいけばな 】 生徒さん募集中!
◎対象 幼稚園時年中〜小学生 定員8名
◎日時10月31日(土)
◎受講料+お花代(前納制)
アトリエ5生徒さん 3,120円(税込)
非会員の方 3,440円(税込)
☆お申し込みは開催日の一週間前までにお願い致します。
お問い合わせ:アトリエ5☎ 044-411-5154
========================