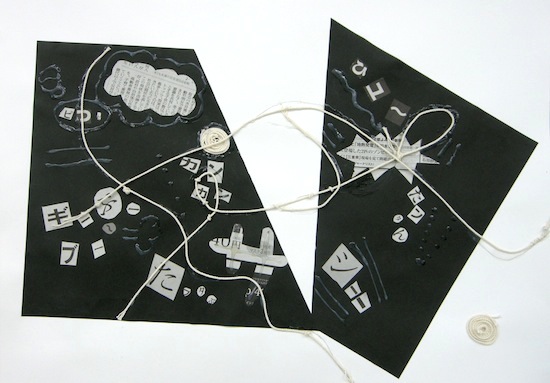[親子クラス] 2014.08.01
渋谷/親子:夏の特別講座
親子クラス 制作:2014年7月
◎講師 / 渋谷 葉子
今年も暑い、あつ〜い夏がやってきました。
そんな中、毎回ちびっこ達が元気にアトリエに通ってきます。
今回は大きな紙に手に絵の具をつけて挑みます!!
水のりのヌルヌル感を心地よく感じたり、霧吹きでシュッ、シュッとにじませたり、
まさに水遊びの感覚でお絵描きです。
こちらのねらい通りに思い切り弾けて、絵の具と戯れる子ども達…
と、みんなが皆んな、そのようにはいかないものです。
毎年、ひとりふたりはいます。ドロドロベタベタ系の嫌いなお子さん。
お母さんは汚れを覚悟で張り切っていらしているのに、何故か嫌がる我が子。
お友達の◯◯ちゃんみたいに、思い切り弾けて欲しいわぁ。
でも、子ども達ひとりひとり性格が違います。
気分を開放させるのに、無理強いは禁物です。
別の紙を用意して、その子の世界を作って楽しんでもらいます。
筆やローラー、クレパスに持ち変えるだけでスイッチの入る子もいます。
大作が仕上がったところで、お楽しみの時間。
ジュースと渋谷初の手作りケーキとでかんぱ〜い♡
8月は通常のレッスンをお休みとし、申し込み制で2回行います。
次に会うのが9月になるお子さんもいます。
夏は日焼けして、たくましく成長する時期でもあります。
今度会うのがとても楽しみです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
親子クラス・生徒募集中
日 時 / 8月6日(水) 10 : 30 〜 11 : 30
内 容 / 絵の具遊び
持ち物 / お着替え、軽食(パン、おにぎりなど)
※8月20日の特別講座は、定員につき募集を終了いたしました。
お問い合わせ ☎044−411−5154