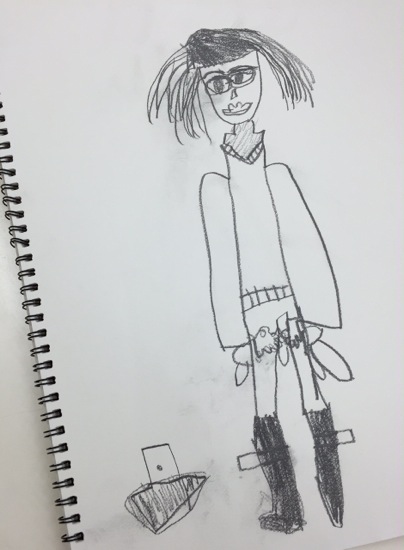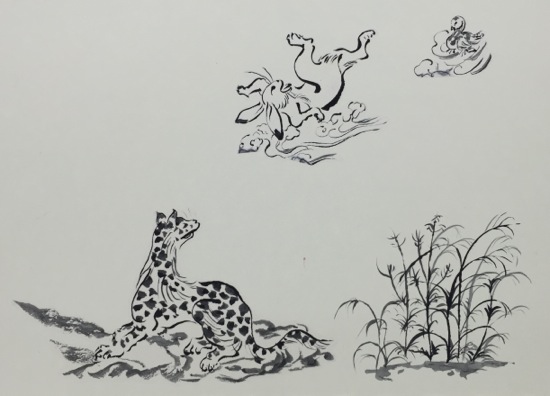[幼児クラス] 2016.01.14
幼児のクロッキー
◎講師:渋谷 葉子/
アトリエ5では年に3回、4月・9月・1月の1週目に取り組んでいます。
お休み明けのウォーミングアップといったところでしょうか。
講師とアシスタントがモデルになり、10分という短い時間で描きます。
お約束として、描いている間は消しゴムを使わないこと。
見ることに集中するよう「間違えたら消せばいい」と甘えないためにはずします。
今回は3回目なので、描く前に今までの成長過程を振り返りました。
言葉掛けはあえて短く「よく見て」「ゆっくり」「ていねいに」
そして、タイマーをセットして描き始めます。
おしゃべりでにぎやかだった部屋もタイマーの「ピッ!」の音で一瞬に静まります。
描いている間は幼児さんといえども、殆どおしゃべりせずに集中します。
タイマーが鳴ったら、スケッチブックを前に並べます。
緊張をほぐす時間と、みんなの作品を見るという点をがポイントです。
次はモデル交代。どんな違いがあるか、みんなで探します。
今回はメガネ。形の特徴のポイントだけを伝えました。
キーワードは「画用紙をたっぷりと使う」
2回目となると子ども達も調子が上がってきて、手が早くなり時間に余裕ができてきます。
そして追加のキーワードは「詳しく見る」
子ども達は細かなところを発見し、形にすることで楽しさを覚えます。
これがクロッキーで一番大切にしていることです。
そして、今しか描けない線、表現を大事にしたいと思っています。
指導を入れてたとえ上手に描けたとしても、それは子ども自身の絵ではなくなってしまうからです。
子どもが観察した中で気づいて、獲得した形に意味があるのです。
ですから、あえて指導は入れません。
実際と違っても、形が小さくても、子どもが描けるようになるその時を待ちます。
スケッチブックはお絵描きの成長記録。
少しづつ変化していく過程に意味があるのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*facebookに写真を追加しました。→☆