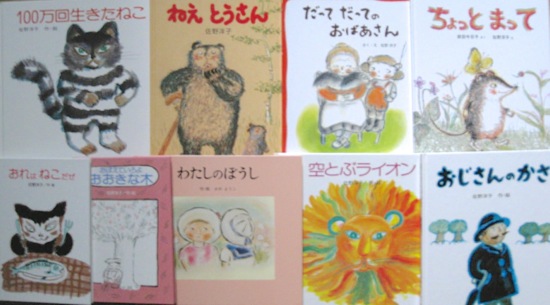[小学生クラス] 2015.07.30
山田/小学生:ぐるぐるドキドキ土器づくり
小学生クラス / 制作:2015年7月
◎感想/講師:山田 稔子(火曜日クラス)
「縄文土器の荒々しい、不協和な形態・文様に心構えなしに触れると、誰でもがドキッとする」とかつて言ったのは、岡本太郎氏。今月の小学生クラスは、粘土と格闘の日々です。先月末のテラコッタ粘土での造形活動も大いに盛り上がりましたが、7月はいよいよ土器作品を作ります!
縄文土器について改めて調べてみると、太古、日本人のルーツに、こんなにも力強く豊かで逞しい表現があったとは実際驚きです。ツルンと無駄のない機能美のデザインに囲まれた現代の生活感覚からすると、いい意味で違和感のあるものばかり。火曜クラスの子どもたちも、ぐるぐる激しい文様や燃えさかる炎のような様々な形をした土器の写真に興味津々。「どれくらい昔の日本?」「なんのための模様なのかなぁ」「顔がついてる!」「こんなのどうやって使ってたの!?」色々と想像を巡らせたり、ただただ不思議な表現に見入ったり。わからないけれど、なんだかスゴイ・・・!!ちょっと戸惑ったようでもありながらすっかりその魅力に捉えられた様子でした。
一万何千年前の日本人の作ったものに、今なお驚く私たち。じゃあ、今の私たちが作ったものに、一万何千年後の人は、驚くかな、ドキッとするかな?そんな目標にもワクワクしながら、制作はスタートしました。
どんな形にしようか?どんな文様や飾りをつけようかな?粘土を捏ねながら、ムクムクとアイデアが浮かびます。「思い描く」感じと「手から生まれる」形にギャップがあったりもしますが、そこを柔軟に受け止めてさらに発展させていけるのが子どもたちの立体造形の面白いところ。触るほどに感覚を磨き上げ、手つきや姿勢も職人っぽく?こなれてきます。飲み込みが早い!頭ではなく、まさに身体でつくっている感じ。縄文時代からの血が、、などというと大げさですが、土を捏ねて何かを作るという行為に、呼び覚まされるような原始的な感覚があるのではないでしょうか。そして、感じながら、考えることを繰り返す。この器の形に飾りはこれでいこう、この道具を使った文様が合うかな。身体・心の動きをも練り込め、目下制作中の子どもたち。作品完成は来月になります。
いきなり私事で恐縮ですが、もうすぐ私は出産を迎えます。経験のないことに不安からつい情報や知識にばかり頼りそうになりますが、レッスンで子どもたちの制作風景を見ていると、自分の感覚に素直に向き合いながら柔軟に考えることを大事にし、来る局面に対峙していこう、と勇気を貰えました。今回の企画を通して縄文土器の文様には安産祈願や出産をモチーフにしたものも多いということを知れたのも、偶然ですがなんだか面白い縁だな、と感じています。逞しく脈打つような、日本人の、人間の根底にある、力。きっと自分にもあるはず、生まれてくる命にもあるはず、どの子もどの人も持っているはず。今こそ、そう信じたいと思います。
産休に入るにあたり、応援して下さったご家庭の皆様に、改めて御礼申し上げます。温かいお声がけやメッセージ、心から嬉しく思いました。火曜クラスの後任には辻が、また幼児クラス後任には渋谷が当たりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。暫く現場からは離れますが、子どもたちの成長、活動の充実を、応援しております!小学生クラス夏の工作完成の報告は、また来月のブログにアップされる予定ですので、どうぞお楽しみにお待ち下さい。