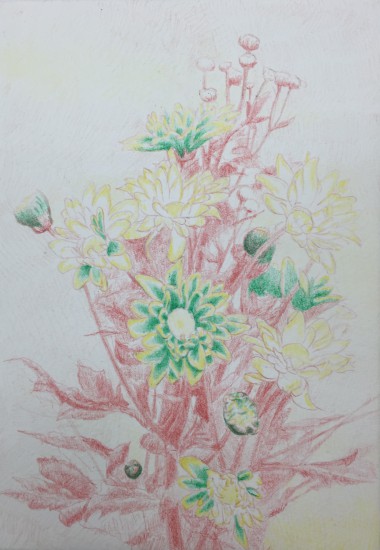[親子クラス] 2016.09.14
アトリエ5のおつきみ
◎講師:渋谷 葉子朝晩、鈴虫の声がにぎやかになり、涼しい風が吹く季節になりました。9月の初回、親子クラスではお月見制作を行いました。これは毎年恒例にしています。導入に「14ひきのおつきみ」の絵本を読みます。ねずみの家族が木の上に登り、お月見をします。空が茜色から夕闇が迫り、お月さまが現れるまでの場面転換が絶妙!お月さまを眺めるシーンではいつの間にか自分がねずみ家族の一員になっている… そして、お月さまと秋の実りに感謝して、家族みんなが手を合わせます。最近は満月を収めようと皆がスマホを向けている光景をよく見かけます。これも時代なのでしょうが、「家族みんなで手を合わせて感謝する」忘れてはいけないことだと思います。絵本の後はサインペンや絵の具で思い思いのお月さまを表現。そして、そのお月さまを眺めながらみんなでお団子を食べます。子ども達にとってはこれが醍醐味!一番の思い出として残るようです(笑)残念ながら今年の十五夜はお天気が悪いようですが、来月の13日は十三夜。この日もお月さまがキレイに見えます。是非、ご家族でお月さまを愛でながら手を合わせ、今ある幸せに感謝致しましょう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ = 親子クラス・秋の生徒募集 = 定員の都合上、一組のみの募集となっております。体験レッスンキャンペーンを行っていますので、通常の受講料1500円→500円に!この機会に是非お越し下さい。【日程】9/21, 10/5,(いずれも水曜日)【時間】10 : 30 〜 11 : 30【対象】2才〜未入園児のお子様【ご予約・お問い合わせ】電話:044 - 411 - 5154(10:30〜18:30 休:日曜日) *お道具はこちらで用意致します。 親子共、汚れてもいい服装でお越し下さい。 尚、新年度の説明会を2月に予定しております。こちらのお申し込みも受付を開始致しました。先着順ですので、お早めにどうぞ。