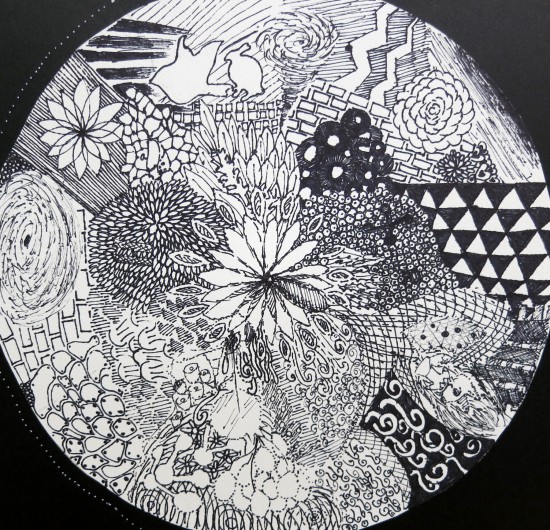[幼児クラス] 2016.10.24
感じて動くその軌跡
こんにちは〜といつも通りにアトリエにやって来た子どもたち。玄関から教室の中を覗いて「わぁ!!」と驚きの表情です。「なんでここにイカがあるの〜?」「たべるの!?」いえいえ。それは、10月の観察画のモチーフだからです。。教室に生のイカ。普段そこにないものが突如として現れる、そのインパクトで子どもたちのワクワクスイッチがONに。駆け寄って集まり、興味津々。触ってみるとどんな感じかな?ヌルヌル、冷たい!足にプチプチがついてる。ちょっと生ぐさい〜。墨が手についた!食べることはあるけれど、まじまじと見たり触ってみることは案外ないもので、五感を使ってみんなと一緒にワイワイ観察する子どもたちの目は驚きと新鮮さで輝いています。さてイカの足って何本だっけ?1,2,3…10本あったね!2本だけが長いんだね。ギョロギョロの目はついてるけど鼻やお口はどこ?イカってクチバシがあったの!?本物に触れて実感したことが自分にとって本当の情報、知識。じっくりたっぷり観察した直後に描く線には、たったいま水あげしたばかりのような「とれとれ」の感動が表れていきます。イカの感触を絵の具の筆にのせてぐいぐい。自分の線、自分の色。幼児さんの観察画は感動画、感じて動くその軌跡です。それは本人のものでしかありません。お手本に沿って教わる描き方ではないので、拠り所は自分の感覚です。う〜ん、いい色出ないかな、、と悩みながらも自分のイメージに手探りで近づこうと試行錯誤。焦らず急がず。いい色だねとそっと声をかけると「でしょ」と言わんばかりに微笑んでくれました。出来たー!の声が上がると、立ち上がって一緒に絵を眺めます。「わ〜いいな!」と自分の絵に大満足。それを自分の考えで実現できたのは、素晴らしいことです。絵の具の発色がのびのび生き生き。それぞれに大きな自信が得られた秋の制作となりました。 【29年度入会説明会】生徒さん大募集!2017年2月23日(木)◎幼児クラス15:00〜15:30来年4月からの入会をお考えの方を対象とした説明会の予約を受け付けています。
アトリエ5の指導方針やカリキュラムの内容等、詳しくご案内致します。また、幼児クラスの通常レッスンのご見学をご希望の方もお気軽にお問い合わせ下さい。アトリエ5☎044 – 411 – 5154(休:日曜日)木・金曜日の14:30頃又は16:00頃にお電話頂けますと、担当スタッフがご案内できます。